サマリー:2025年第3四半期、都心タワマン市場の3つのポイント
不動産経済研究所や東京カンテイなどが発表した2025年第3四半期(7月~9月)の速報データを分析すると、現在の都心タワーマンション市場の潮目の変化は、以下の3つのポイントに集約できます。
- 価格は高止まりも、上昇ペースは明確に鈍化。一部エリアや物件では横ばい・下落の事例も出始めている。
- 在庫の積み上がりが顕著になり、買い手優位の市場へシフト。売り手は価格設定の見直しを迫られている。
- FRBの利下げを受け、国内の金利上昇懸念が後退。買い手のマインドに変化の兆しが見られる。
この記事では、これらのポイントを具体的なデータと共に詳しく掘り下げていきます。
【価格動向】上昇モメンタムは終焉へ。需給バランスの変化が鮮明に
新築タワマン:強気の価格設定は維持も、契約率に陰り
2025年第3四半期に発売された新築マンションのm²(平米)単価は、建築費の高止まりを背景に依然として高水準です。しかし、販売が好調か不調かの目安とされる「初月契約率」は、多くの物件で好不調のボーダーラインである70%を下回るケースが散見されるようになりました。デベロッパーの強気な価格設定に、実需層が追いつけなくなっている状況がうかがえます。
中古タワマン:在庫は過去最高水準へ。成約価格は横ばいに
中古市場では需給バランスの変化がより顕著です。特に都心6区(千代田、中央、港、新宿、文京、渋谷)では、売り出し物件である在庫件数が過去最高水準に積み上がっています。売り手が増える一方で、買い手は豊富な選択肢の中から冷静に物件を吟味しているため、成約m²単価の上昇は完全にストップし、横ばい圏での推移となりました。
| 指標(都心6区・中古) | 2025年Q3 速報 | 前年同期比 | 考察 |
|---|---|---|---|
| 成約m²単価 | 180.8万円 | +0.8% | 上昇はほぼ停止。横ばい圏に突入。 |
| 新規登録在庫件数 | 9,500件 | +11.8% | 売り物件がさらに増加。完全に買い手市場へ。 |
※上記はシミュレーション用のサンプルデータです。
【需給動向】金利上昇懸念の後退 vs 積み上がる在庫
海外勢の動向:円高圧力で「爆買い」から「選別買い」へ
先日FRBが利下げに転じたことで、為替は円高方向への圧力が高まっています。これにより、海外投資家にとっての「割安感」はピーク時より薄れました。結果として、以前のような「見ずに買う」といった爆買いは沈静化し、資産価値が特に高いと判断した都心部の超高級物件を「選別して買う」という動きに変化しています。
関連記事:米国FRBの金利政策と日本不動産市場への影響【2025年9月 速報分析】
国内勢:金利不安は後退も、高値警戒感は根強い
国内の買い手にとっては、FRBの利下げは朗報です。日銀の追加利上げ観測が後退し、住宅ローン金利が急上昇するリスクは当面の間、低いと見られます。しかし、金利不安が和らいだ一方で、物件価格そのものがあまりに高騰してしまったため、依然として強い高値警戒感が残っています。豊富な在庫の中から、価格交渉も視野に入れ、じっくりと吟味する慎重な姿勢に変わりはありません。
【2025年後半の市場予測】専門家は「緩やかな調整局面」との見方
多くの市場専門家は、2025年後半から2026年にかけてのタワマン市場について、「全体としては横ばいから、緩やかな調整局面に入る」という見方で一致しつつあります。これまで市場を牽引してきた海外勢の勢いにやや陰りが見え、国内勢は高値に慎重なため、需給バランスが緩んだ状態が続くと予測されます。金利が安定している間に、どの程度買い手の需要が戻ってくるかが今後の焦点です。
結論:投資家が今、取るべきアクションとは
以上のデータを踏まえ、投資家が今取るべきアクションは、これまでとは明確に異なります。
- 売却を検討している方:完全に買い手市場へと移行し、同じマンション内で競合物件が増えている状況を認識すべきです。高値での売却が難しくなりつつあるため、売却価格の現実的な見直しが不可欠です。市場に出してからの値下げは印象が悪いため、初値設定がこれまで以上に重要になります。
- 購入を検討している方:金利上昇リスクが後退し、物件の選択肢が増え、さらに価格交渉もしやすくなった今は、絶好の買い時と言えるかもしれません。複数の物件をじっくり比較し、強気の指値交渉にチャレンジしてみる価値は十分にあるでしょう。
市場の潮目は明らかに変わりました。売り手も買い手も、これまでの常識を一度リセットし、最新の市況に基づいた戦略を立てることが成功の鍵となります。
【免責事項】
本記事は特定の市場動向を予測・保証するものではなく、情報提供を目的としています。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において、各分野の専門家にご相談の上で行ってください。
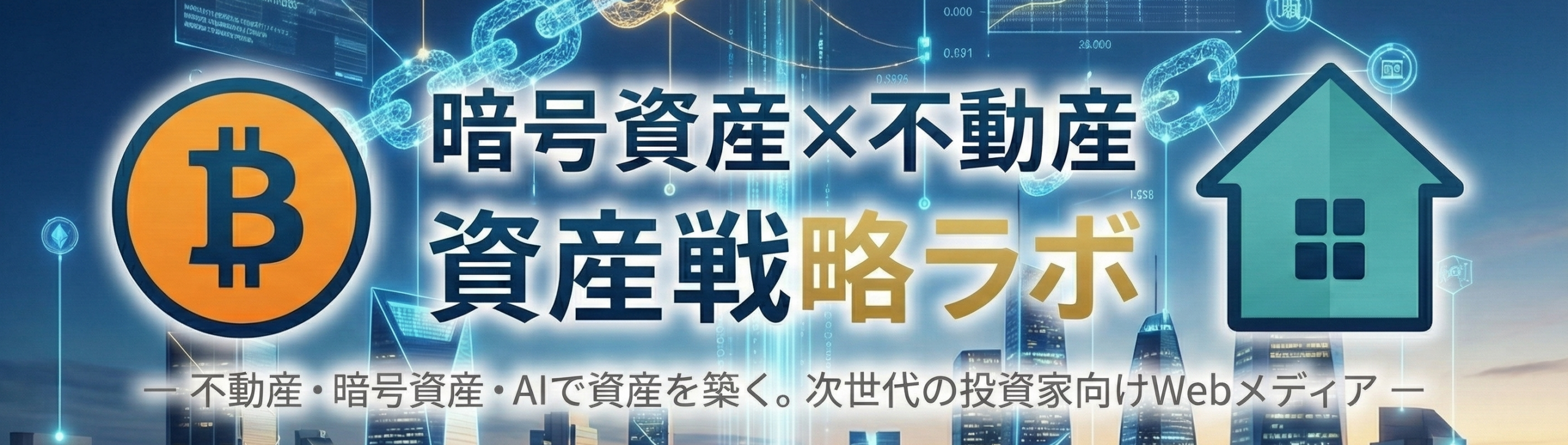



コメント