不動産投資の成功は、利回りや稼働率だけでは決まりません。手元にどれだけキャッシュを残せるか、つまり「節税」も極めて重要な要素です。そして、その節税の第一歩こそが、経費を漏れなく、正しく計上することに他なりません。
「これは経費になるのかな?」と迷う項目を一つずつクリアにすることで、あなたの確定申告は万全なものとなり、手取り収入は大きく変わる可能性があります。
この記事では、不動産投資において経費として認められる代表的な項目を、プロがチェックする5つのカテゴリーに分けて、20個の項目を具体的に解説します。
【不動産投資における経費の基本】
不動産投資における経費とは、「不動産収入を得るために直接必要だった費用」のことです。ご自身のプライベートな支出と、事業のための支出は明確に分ける必要があります。
物件の「取得」にかかる経費
物件購入時に支払った費用の一部は、経費として計上できます。
- 不動産取得税: 不動産を取得した際に、一度だけ課税される税金です。
- 登録免許税: 不動産の所有権を登記する際に必要な税金です。
- 印紙税: 売買契約書に貼り付ける印紙代です。
- 司法書士への報酬: 所有権移転登記などを依頼した司法書士に支払う手数料です。
物件の「管理・運営」にかかる経費
ここが経費のメインパート。日々の運営にかかる費用です。
- 管理委託費: 管理会社に支払う、物件の管理や入居者募集の委託手数料です。
- 修繕費: 壁紙の張り替え、給湯器の交換、エアコンの修理など、物件の原状回復や維持管理のための費用です。※注意!修繕費 vs 資本的支出 修繕費は一括で経費にできますが、物件の価値を高めるようなリノベーション(例:部屋数を増やす、グレードの高い設備に入れ替える)は「資本的支出」と見なされ、減価償却で数年に分けて経費化する必要があります。判断に迷う場合は、必ず専門家にご相談ください。
- 減価償却費: 不動産投資における最大の経費です。建物や設備は年々価値が下がっていくという考え方に基づき、その価値の減少分を、実際にお金が出ていかなくても経費として計上できます。
- 損害保険料: 火災保険や地震保険など、万が一の事態に備えるための保険料です。
- 消耗品費: 共用部の電球や、簡単な修繕に使う工具、文房具など、少額の備品購入費です。
- 通信費: 物件管理のための電話代やインターネット料金など、事業に使った分を按分して計上します。
- 交通費: 物件の視察や管理会社との打ち合わせ、不動産投資セミナーへの参加などでかかった電車代やガソリン代です。
関連記事:不動産投資の出口戦略|個人と法人、売却時に得をするのはどっち?税金の違いを比較
「ローン」に関する経費
金融機関からの借入金に関する費用も経費になります。
- 支払利息: ローン返済額のうち、利息部分のみが経費の対象です。元本部分は経費になりません。
- ローン保証料: 金融機関から融資を受ける際に、保証会社に支払う保証料です。
- 団体信用生命保険料: ローンに付帯する団信の保険料も経費計上できます。
納める「税金」も経費になる
税金の中にも、経費として認められるものがあります。
- 固定資産税・都市計画税: 物件を所有している限り、毎年課税される税金です。
- 事業税: 不動産所得が290万円を超えた場合に課税されることがある税金です。
【見落としがち】意外と認められる経費
ここからは、多くの人が見落としがちな、しかし正当に認められる経費です。これらを計上できるかどうかで、納税額に差がつきます。
- 新聞図書費: 不動産投資に関する専門書、雑誌、新聞の購入費用です。情報収集は事業の一環と見なされます。
- 接待交際費: 管理会社や不動産業者の担当者との打ち合わせでかかった飲食代などです。事業に関係する相手との良好な関係を築くための費用と認められます。
- 税理士への報酬: 確定申告を依頼した税理士に支払う顧問料や手数料も、もちろん経費になります。
- 勉強代(セミナー参加費など): 不動産投資に関する知識を深めるためのセミナーや勉強会の参加費用です。
関連記事:【不動産投資家向け】マイクロ法人設立のメリット・デメリットと、節税効果を最大化する3つのポイント
【まとめ】領収書一枚から、あなたの節税は始まる
今回ご紹介した20個の経費項目、いくつご存知でしたか? 大切なのは、これらの経費を漏れなく、正確に記録し、証明できることです。日頃から領収書やレシートをきちんと保管し、会計ソフトなどを活用して管理する習慣をつけましょう。
経費計上の判断は、時に専門的な知識を要する場合があります。少しでも不安に思ったら、あるいは節税効果を最大化したいと考えるなら、必ず税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、個別具体的な税務アドバイスを提供するものではありません。経費の計上や確定申告に関する最終的な判断は、ご自身の責任において、税理士などの専門家にご相談の上で行ってください。
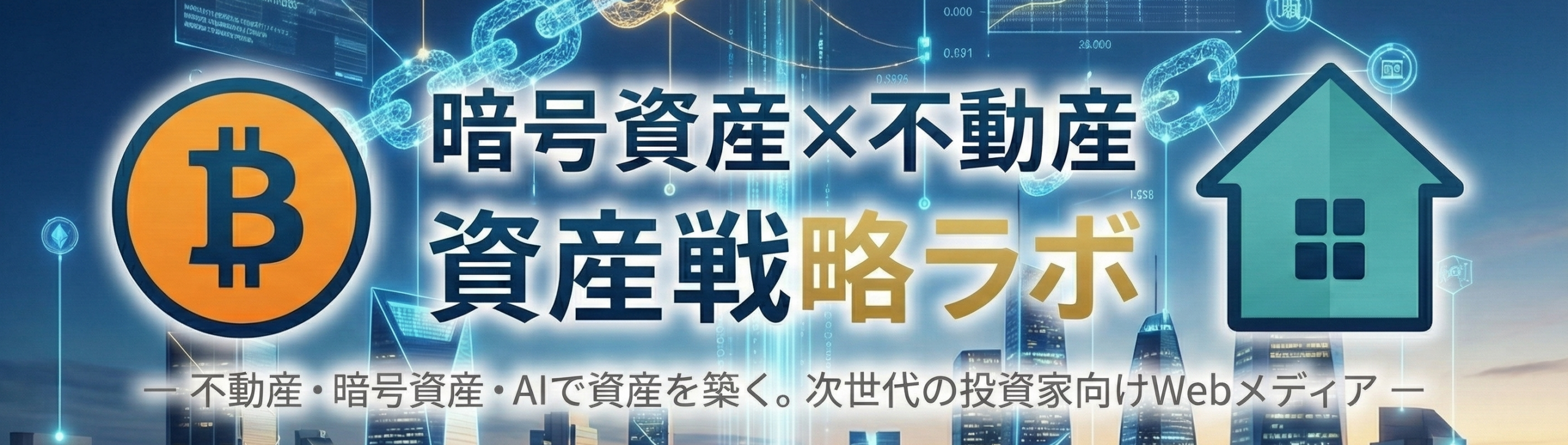

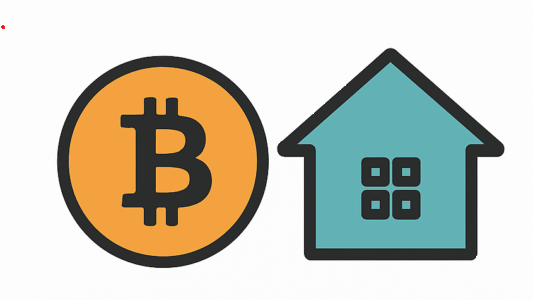
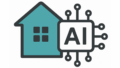
コメント