【2025年税制改正】最大のポイントは法人の「期末時価評価課税」の見直し
2025年における暗号資産の税制改正で、最も大きなインパクトを持つのが法人税における「期末時価評価課税」ルールの変更です。これは、特に暗号資産を長期で保有したいと考える企業や、Web3.0関連事業を行うスタートアップにとって、長年の課題でした。
これまでの課題:法人が暗号資産を保有しにくい「含み益への課税」
これまでのルールでは、法人が事業年度の期末に暗号資産を保有している場合、その時点での時価で資産を評価し、帳簿上の価格との差額(含み益)に対して課税されていました。つまり、まだ売却して利益を確定していないにもかかわらず、税金を支払う必要があったのです。これにより、運転資金が圧迫されることを恐れ、多くの企業が日本国内で暗号資産を長期保有することをためらう原因となっていました。
【変更点】「暗号資産ロック」の活用で、期末の含み益課税は回避可能に
今回の税制改正により、法人が保有する暗号資産であっても、「継続的に保有する」など一定の要件を満たすものについては、期末時価評価課税の対象外となりました。
そして、この適用除外を受けるための具体的なアクションが「暗号資産ロック」です。これは、bitFlyerやCoincheckといった国内の大手暗号資産取引所が提供する「ステーキング」や「レンディング」サービスを活用し、保有する暗号資産を一定期間動かせない状態にすることで、『短期売買目的ではない』という税務上の要件を満たす、現在最も一般的で有効な手法です。
これにより、法人は含み益への課税を心配することなく、暗号資産を長期的な視点でポートフォリオに組み入れることが可能になります。これは、日本のWeb3.0推進における大きな一歩と言えるでしょう。
個人の暗号資産税制はどうなる?「申告分離課税」への道
一方で、多くの個人投資家が最も関心を寄せている「個人の税制」については、どうなったのでしょうか。
現状のルール:最大55%の「総合課税」と不利な損益通算
2025年現在、個人の暗号資産取引で得た利益は「雑所得」として扱われ、給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象です。これにより、所得が多い人ほど税率が上がり、住民税と合わせると最大で55%にもなります。さらに、株式投資のように損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」や、他の金融商品の利益と相殺する「損益通算」も認められていません。
【2025年の動向】申告分離課税への変更は「検討事項」。今後の議論に注目
株式投資などと同じように「一律約20%の申告分離課税にしてほしい」という要望は、投資家や業界団体から長年強く出されています。2025年度の税制改正大綱でも、この点は重要な「検討事項」として明記されました。
しかし、2025年時点ではまだ「決定」には至っていません。政府・与党内で議論は続いているものの、具体的な変更時期は示されていないのが現状です。個人の税制については、引き続き今後の動向を注意深く見守る必要があります。
この改正が不動産投資家に与える影響
今回の税制改正は、不動産を主軸とする投資家にとっても無視できない変化をもたらします。
資産管理会社で暗号資産を保有するメリットが増加
期末時価評価課税のルールが変更されたことで、不動産投資のために設立した資産管理会社(マイクロ法人など)で、暗号資産を長期保有する戦略がより現実的になりました。これまでは含み益への課税がネックでしたが、今後は法人内で不動産と暗号資産の両方を、腰を据えて運用しやすくなります。
関連記事:【完全ガイド】資産管理会社の作り方|不動産・暗号資産・AI投資で資産を爆増させる最強活用シナリオ3選
個人での利益確定は、引き続き税率を意識した戦略が必要
個人の税制に変更がない以上、個人名義で大きな利益が出た場合の税負担は依然として重いままです。不動産所得など他の所得と合算して課税所得が大きくなる方は、利益確定のタイミングや、法人での保有に切り替えるかどうかを、より慎重に検討する必要があるでしょう。
まとめ:法人のルールは改善、個人のルールは注視が必要
2025年の暗号資産税制は、「法人にとっては追い風、個人にとっては現状維持」とまとめることができます。法人の期末時価評価課税の見直しは、間違いなくポジティブな変化です。一方で、多くの個人投資家が望む申告分離課税への移行は、実現に向けた議論が続いているものの、まだ少し時間がかかりそうです。
税金のルールは、投資の成果を大きく左右する重要な要素です。常に最新の正確な情報を入手し、ご自身の投資戦略に活かしていくことが求められます。
関連記事:【2025年最新版】不動産投資家目線で考える。暗号資産の利益、個人と法人どちらが有利?
【免責事項】
本記事は情報提供を目的としており、金融商品の売買や特定の税務・法務戦略を推奨するものではありません。税制は非常に複雑であり、個々の状況によって適用が異なります。実際の税務判断にあたっては、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
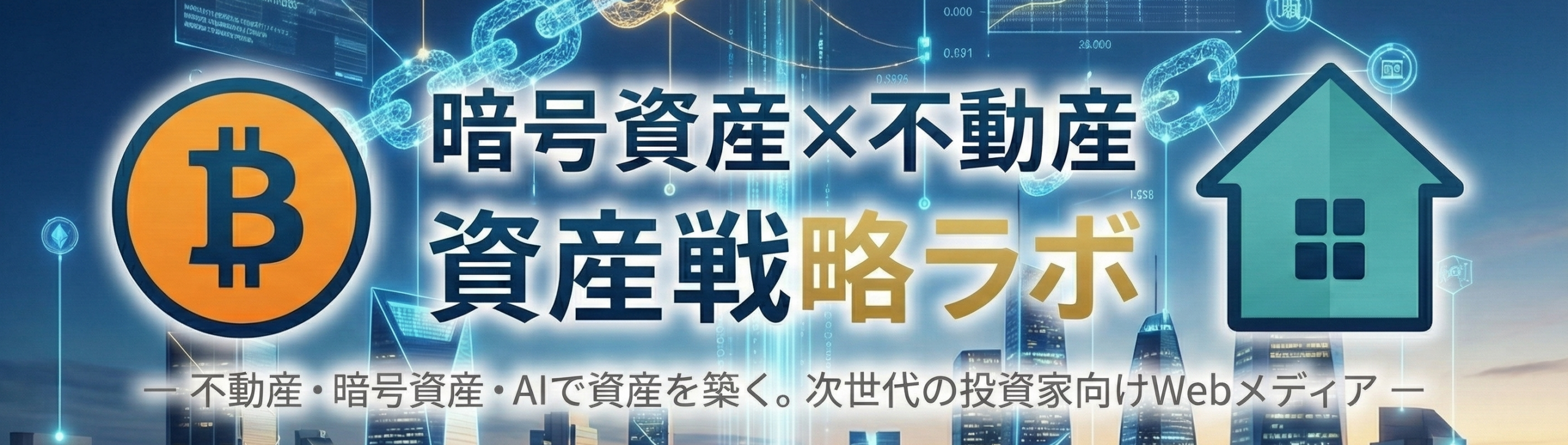

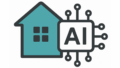

コメント